|
ガッシャァアアアア───ン─… ゴォワン…ゴワン…ワン……
高らかに鳴り渡る金属音。それと共にそこら中にぶわっとばかりに舞い上がる白い粉。 「マヤ様っ、いーかげんにして下さいっっ!!」 床からもうもうと立ち上る白い煙、その小麦粉の霧の中でついに美和の怒りの雷が落ちた。 「…ご、ごめんなさいぃぃぃ〜〜〜〜〜」 しゅんと俯いて、髪から足元のスリッパまで、全身真っ白になったマヤが、肩をすぼませて身を小さ くしている。 「でも… でもぉ……」 うにゃうにゃと口の中で言い訳をしようとするマヤに、美和はため息をつきながら彼女の頭の粉を払 ってやる。 「もうそろそろ、諦められたらいかがです?」 「それはイヤっ! ぜぇっったいに、真澄さんに食べてもらうんだからっ」 鼻息も荒くそう宣言すると、マヤは床に転がったステンレス製のボウルを拾い上げ、とりあえずとそ の中に飛散した小麦粉を片していく。 「あぁ、マヤ様、私が片付けますわ。それよりシャワーを浴びてらっしゃってください。全身粉塗れで すよ」 「いーよいーよ。だって私が汚しちゃったんだもん。ちゃんと自分で…って、きゃぁああ」 今度は先ほど床にこぼしたままだったバターに、ついていた膝が滑ったらしい。 マヤの手から小麦粉の入ったボウルが、またしてもふわりと宙を舞う。 ───グアッシャンッ! 「マ〜ヤ〜さ〜ま〜〜〜───…」 再度立ち上る煙幕の中で、美和の怒りを込めた低い声が地を這うようにして響いた。 「うっっ…ごめん…美和さん。や、やっぱり私、大人しくシャワー浴びてきます……」 「是非とも、そうなさって下さい!」 間髪入れずの美和からの返答に、すごすごとキッチンから退場するマヤの後姿を見ながら、美和は はぁあああ〜〜と肺からいっぱいのため息をついた。 チロッと視線を返せば、キッチンテープルの上にはページを広げた状態の1冊の本がのっている。 タイトルは『はじめてのお菓子作り』。 広げられてるページは『チョコレートケーキ』の作り方だ。 そのページを恨みがましく見詰めながら、美和は床に散った小麦粉やらバターをやれやれ、と片付 け始めた。 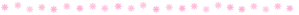 2月14日、St.バレンタインデー。世の乙女が心ときめかせる、日本中がチョコレートにまみれる日。 その前日、マヤは比較的早い時間に、大きな荷物を両手に抱えて屋敷へと帰宅してきた。 「おかえりなさいませ、マヤ様。何だか…すごい荷物ですね。どうなさったんですか?」 マヤの手から大荷物を引き受けながら、何気なく美和は訊ねる。 「やっだなぁ、美和さん。明日はバレンタインデーだよ。だから帰りにデパート寄って、明日配るため のチョコレート買ってきたんだ」 あ〜重かったっ!というマヤの言葉どおり、大きな紙袋2つに満載の量の箱がぎゅうぎゅうに詰め 込まれている。 ぱっと見では一体いくつ数があるのか、ちょっと見当がつけられないくらいだ。 「ずいぶんと沢山買われたんですね」 「うん、だってお世話になってる人にちゃんと配んないと。今度の舞台で共演する久留巳さんや木村 さんとか、監督さんや現場のスタッフの人とかぁ…」 そう言いながら、マヤは指折り次々と交友男性の名を上げていく。 地味だの目立たないだの芸能人らしくないだのとは、つね日頃からマヤ本人の弁であるが、やはり そこは痩せても枯れても業界人。その数たるや半端なものではない。 マヤの指折りが2往復目に入った頃、そうだっと手を打って、 「それに桜小路くんや黒沼先生にも渡したいし!」 サクラコウジ… マヤの口から出たその名を聞いて、美和は一瞬ぎょっとする。 相変わらずこの少女ときたら、何の気なしにこのような爆弾をひょいと投下するのだから、心臓に悪 い。 美和相手ならともかくとして、マヤを盲目的に愛してるこの屋敷の主人、真澄が相手でも、平気で ぺろっとそんな発言をかます。 その度にやがて互いに大声を上げての言い争いに発展するというのに、どうも見ていると全く懲りる 様子が無い。 最近ではもしかしたらマヤは、ムキになる真澄を見たいが為に、わざとやってるんじゃないのかと疑 いの目を持ってしまいそうなくらいだ。 「…マ、マヤさまっ。それで真澄様へのチョコレートは、どんな物を用意なさったんですか?」 「うんっ、チョコレートケーキ買ってきたんだ♪」 「ケーキ…ですか?」 つい聞き返してしまった。 それはそうだ。そもそも真澄は甘いものなど好んで食べたりなどしない。 普段の食事からして、食後のデザートなど食べるのはマヤばかりで、真澄は付き合いにせいぜいフ ルーツを少し口にする程度だ。 それでもマヤから贈られたとなれば、喜んでチョコレートのひとつやふたつ食べそうだが、だったらな にも嫌がらせのようにカサを増したケーキなどにしなくてもいいようなものだが… 意外げな美和の顔を見ながら、マヤは意気揚々と答える。 「だってどうせ真澄さん、『おれは甘いものなんて食わない』とか言うに決まってるもん。きっと一口 か二口くらいしか食べてくれないよ。それで私に回ってくるなら、私が食べたい物を用意した方がい いと思わない? このケーキね、お店で見たときからすっごく美味しそうで、食べてみたかったん だ〜」 なるほど。 大いに納得してしまった。 たしかにそれはありえそうな話しだ。 真澄にしても、自分が食べるよりも、美味しそうにケーキをほおばるマヤを眺めている方が、いかに も嬉しいだろうと思う。 珍しくマヤにしては的を得ている発想だわ…などと、暢気にも思っていた美和であった。 思えばこの時に、美和はもう少しマヤから突っ込んだ話しを聞き出し、気付いて、彼女にしっかりと 言い含めておくべきだったのだ。 だが何事においても、ついうっかりという事はある。 だからこそ、後の祭りという言葉が存在するのだ。 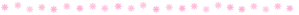 バレンタイン当日。 夜、食事を終え、リビングで食後のコーヒーを飲んでいた真澄の元へ、マヤはいそいそと背中に ケーキの箱を隠しながら忍び寄り、 「真澄さんっ!」 わっ!とばかりに、背後からいきなり大声をかける。 すると真澄は、口に含んでいたコーヒーをぐっと喉に詰まらせたらしい。うっ…と呻いた後、ごほごほ と幾度かの咳払いをし、 「マヤっ、おどかすんじゃないっ!」 そう言いながら、ぐるりと振り返った彼の目の前に、マヤはずいっと箱を差し出す。 「はい、どうぞ。バレンタインチョコです。えへへ、あの…だんな様に……」 使い慣れない『だんな様』という単語に僅かにテレを混じらせながら、マヤはにこにことした笑顔を真 澄に向けた。 イキナリ眼前に突きつけられた代物に、一瞬びっくりと目を見開いていた真澄だったが、やがて 徐々に口元をほころばせた。 「そういえば、今日は2月14日か。うっかりしてたな」 マヤの手からかなり大きめの箱を受け取りながら、そんな事を言う彼に、マヤは小首をかしげる。 「なんで? 会社の女の子からいっぱい貰わなかったんですか? ほら、水城さんからとか」 「…水城くんが俺にチョコレートを?」 冗談だろう?という感じで問い返せば、なんで?とばかりにきょとんとした顔で見詰め返される。 どうやらしごく真面目に言ったらしい。 今日も東京中をせわしなく移動する自分に付き従いながら、見事な手腕でスケジュールを捌いてい た水城が、仕事の合間に「真澄様、バレンタインですから…」などと、世の女性達を習って愁傷に自 分にチョコレートを手渡す…… 想像すると確かになかなか面白い図ではあるが。 真澄はついぷっと笑いが漏れた。 「いや、あいにく彼女からは何も貰ってない。それに、今日は1日ほとんど外に出ていたからな…」 「えーっ。じゃあ真澄さん今日まだ全然チョコ貰ってないの?」 「そうなるな」 「うそ〜〜〜。ゼッタイゼッタイ山みたいに貰ってくると思ってたのに!」 大声を上げて驚愕するマヤ。 そんな様子の彼女を、まるで面白いオモチャを見るような気持ちで真澄は眺める。 本当の事を言えば、真澄宛のチョコレートならば、毎年各所から山のように贈られている。 何と言っても「鬼社長」のレッテルが貼られているとはいえ、この容姿にこの姿形の男である。更に は社長という肩書きまで付けば、遠目から見る分には、充分女性の理想の男性像であろう。あくま で遠目から見る分には。 マヤと結婚した現在でも、社内でも社外でも、いまだ根強いファンが数多居るらしい。 それ故贈られるチョコもなかなか素晴らしい量なのだが、ただしそれは秘書室付けでストップする 為、実際に真澄の手に渡るということはまずほとんどないのだ。(たまたま通りかかった真澄に、直 接手渡してくる剛の者が、ごくたまに居たりはするが) その辺りの処理も(受け取り&適当な処分&義務のお返し)、この時期の真澄付きの秘書達の仕事 のひとつとなっている。 だがそんな事は、もちろんマヤが知るはずも無く、また真澄もわざわざ教える気も無く… 「もうっ! 真澄さんがあんまり会社で怖い顔ばっかりしてるから、女のコたちが尻込みしちゃうんで すよ」 「別に貰いたい人からはこうして貰えたんだから、構わんさ」 平然とそう言い放つと、視線で開けていいか?と問われる。 マヤが頷くと、真澄は器用に包装紙を解き、箱を開ければ大きなハートをかたどったチョコレート ケーキが現れた。 「ありがとう。……しかし、ずいぶん大きいな」 「だ〜いじょうです。真澄さんが食べきれないなら、私が食べるし♪」 「それ、狙ってただろ?」 にやっと笑いながら真澄が突っ込むと、えっへっへーと、マヤはばれた?とぺろりと舌を出す。 この時点までは、非常に穏やかで甘甘ムードな二人だったのだ。そう、この時点までは。 問題はこの後、またしても爆弾娘が何の気なしにぽろっと漏らした一言からはじまった。 「でもここのチョコケーキ、ホントに美味しいんですよ。私も今日味見したから、間違いないです」 だってね…とそのまま話しを続ける。 「桜小路君とか黒沼先生にだって好評だったんですから!」 ……つくづく、どうしてこう余計なことをぽろぽろと言うのか。 本当にこれが本人に言わせると、決してわざとじゃないというのだから、ひたすら始末が悪いと思 う。 予想通りというか、分かった結果というか、直後真澄のこめかみにピキッと血管が浮き出した。 「…何だって?」 急に彼の声色が変わったことに、マヤも瞬時に自分がなにやらまずい事を、またしても口にしてしま ったらしいと今更気付く。 「あ、あれ? …えっとぉ、その、私、なんか言ったかなぁ〜〜??」 あははっと、笑って誤魔化そうとしても、この男にそんな物が通用するわけも無く。 「ほぅ… 君は桜小路たちに贈った物と同じ物を、夫である俺に贈ったのか?」 どすの効いた声で凄まれて、マヤはうっ…と詰まった後、ごにょごにょと拙い言い訳を始める。 「あの、あのねっ。一緒じゃないんだよ。ちゃんと真澄さんの方がおっきいサイズのやつなの。桜小 路君や黒沼先生や、久留巳さん達には、もっとちっちゃいサイズのヤツをね、あげたの」 …だからっ、どうしてそこでわざわざ新たな男の名を付け加えたりするのかっっ。 真澄は、いよいよ仏頂面に拍車がかかっていく。 「ほらっ、でもこれホントにすご〜く美味しいんですってば。こう見えてけっこう甘さ控えめでしたか ら、きっと真澄さんにも食べられますよ」 なんとかマズイ話題を煙に巻こうと、話しの矛先を変えたつもりだったが、変えた先もまたマズかっ た。 「そうか…そういえばさっき、今日味見したとか言ってたな。一体どこで味見したんだ?」 「え? えぇっとぉ… その、わ、忘れちゃったっ!」 「ほぉ〜〜〜…」 不機嫌がありありと混じったその声に、マヤはやばいっと縮こまっている。 「…と、とりあえず、真澄さん、折角だから、その、試しに食べて…みません?」 おずおずと言ってみると、 「……」 無言の沈黙で返されてしまった。どうやらかなりのご立腹らしい。 どうやって真澄の機嫌を取り直そうかとマヤがあれこれと思案し始めた直後、突然真澄がケーキを 箱に戻し始めた。 「やっぱりこれは受け取らない。返す。君が食べなさい」 箱ごとそう言って押し返され、マヤは目をぱちくりと見開いた。 「え?え?え?」 「聞えなかったか? 俺はいらない。受け取らない」 ふんっ!とそっぽを向く。 「えーっ、だって、折角用意したんですよ。ちゃんと受け取ってください!」 「いやだね」 と駄々をこねられて、マヤはそんなぁと声を上げる。 いくら箱を差し出そうとも、頑として真澄は受け取ろうとはしない。 「大体、そもそもなぜ市販品なんだ? 他の男どもへの義理ならともかく、俺に贈るものは君が手作 りしてくれるのが当然じゃないのか?」 「そんなのっ! 私が不器用なこと、真澄さんだってよく知ってるでしょッ!」 「そこを押して頑張って作ってはくれないのか」 「私だって出来るなら手作りしたいですっ。でもそれで、もしかお腹壊しちゃったりしたら、どーするの よ」 「ともかく!市販品のケーキなんて俺は受け取らない。俺に貰って欲しいなら、君が手作りするん だ」 その日、えーーーっっ!!というマヤの大悲鳴が、速水家の屋敷にこだました。 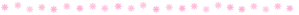
次の日から、マヤは仕事から帰宅したその足で、屋敷のキッチンに閉じ篭り、悪戦苦闘する日々が 続いた。 目標は真澄に受け取り拒否された、ハートの形のチョコレートケーキ。 最初は速水家のおかかえシェフの指導が入っていたのだが、もともと彼は人に教えるというのが下 手だったのと、くわえてあまりのマヤの不器用ッぷりにそうそうに白旗を上げて退散してしまった。 美和は今までの経験から、そこそこマヤのドジには免疫があるので、辛抱強く付き合っていたのだ が… それでもさすがの美和も、ここまでとは…と冷や汗が流れまくる状態であった。 ともかく失敗するにしても、度合いが半端でないのだ。 メレンゲの泡立てが足らず、ろくにスポンジが膨らまなくて、なおかつカットしてみれば中が半生だっ たことなど、可愛いものだ。 こんなに膨らまないのはベーキングパウダーが足りないせいだと、今度は異常なまでに増量して入 れたため、それを試食させられた美和はずいぶんと気持ち悪くなってしまった。 デコレーションのチョコクリームにしても、チョコレートを刻むのに夢中で、火にかけていた生クリーム を思い切り失念し、真っ黒に鍋を煮焦がしてしまった。 さらにはスポンジに打つ為のシロップを作れば、本来砂糖と水が溶けたら火を止めてから加えなけ ればいけないブランデーを、ついうっかり、とばかりに火にかけたまま、しかも凄い量を注ぎいれて、 巨大な火柱を立ち上がらせ、あやうく火事をおこしかけた。 …ともかく、もはや戦場といって決しておかしくない状態だ。 冒頭のように小麦粉が煙幕となり、生クリームやメレンゲは泡立てるごとにそこら中に飛び散り、ま るで礫爆弾だ。 この惨状に、初めは半分心配して、半分興味深々でぞくぞくと集まっていた速水家の他のメイド達 も、恐れをなしてクモの子を散らすように居なくなってしまった。 そして今やマヤのこの奮闘に根気よく付き合っているのは、美和ひとりという状況なのだ。 しかし、この状態がほぼ毎日続いてすでに半月以上、そろそろ美和の限界も近い。 マヤがチョコレートを刻もうと包丁を手にする度ハラハラし、いっそ清清しいまでに汚れまくるキッチン を毎度片付け、なおかつマヤの力作(?)が出来上がる毎に、どう?と試食係を頼まれる。 美和はここ半月で表情はげっそりとやつれながらも、食べ過ぎによるウエストのサイズUPに苦しん でいた。 不味いものを無理矢理食べての体重増加。1番嫌な太り方だ。 本音を言えば、美和もいい加減逃げ出したいくらいなのだが、とある所からこっそりと切実に頼まれ てもいたりする。 「美和、お願いねっ! 今、会社も年度末で忙しいのよ。こんな時に真澄様に食あたりで寝込まれ るわけにはいかないわ。あなたが最後の砦なんだから… くれぐれも、頼んだわよっ!」 ……人事だと思って。 最近では美和の飲み友達になっている彼女には、見返りとして、今度高いワインでも奢ってもらわ ねばなるまい。 だがしかし、もう限界ぎりぎり、これ以上続いたらいかに美和といえど白旗を掲げそうになっていた そんなある日、ふらりと救世主が現れた。 |
   |