|
ある日マヤは屋敷にひとりの女性を伴って帰ってきた。
マヤより少しだけ身長の高い、華奢で小柄な女性。 迎えに出た美和と視線が合うと、彼女はにこやかに微笑みながら軽く会釈をする。 「ただいま、美和さん。連絡してなかったんだけど、今日はちょっとお客様が一緒なんだ」 マヤはそう言うと、横の彼女を美和に紹介する。 「美和さんも知ってるよね、こちら、女優の雪田硝子さん」 「えぇ、勿論ですわ。ようこそ、いらっしゃいました」 丁寧に一礼をする美和に、彼女は軽やかなソプラノの声を出して答える。 「突然お邪魔しまして、申し訳ありません。マヤさんに誘われて、図々しくもお邪魔してしまいまし た」 「やだ、硝子さん、私が無理矢理お願いしちゃったんじゃないですか。お忙しいのに、本当にごめん なさい」 焦ってそう訂正しながら、ぺこんっと彼女に対し頭を下げるマヤだが、美和にしてみればなんの事 かさっぱり分からない。 「とりあえず、こんな所では失礼ですし…マヤ様、雪田様をリビングにご案内してよろしいですか?」 「うんっ、お願いします」 リビングのソファに向かい合って座り、楽しげに談笑するマヤ達を背に、美和は片隅でお茶を用意す る。 雪田硝子。 今マヤが稽古に入っている新春からの舞台で共演する女優だ。 元々実力派女優としての呼び名の高い彼女は、過去、数多くの舞台に主演してきた。 清純な乙女の役から、退廃的な悪女、悲劇の女王役まで、その芸域の幅は広い。 マヤが本能と感性で役柄を作り上げるのとは対照的に、彼女は培った経験と緻密な計算によって その役柄を作り上げ、役者としてはどちらかといえば姫川亜弓のそれに近いだろう。 最近は舞台よりも映画の世界にその活躍の場を移し、長い間舞台からは遠ざかっていたのだが、 今回は監督のたっての希望で出演が決まったらしい。 紅天女であるマヤと彼女の共演は、この所の演劇界の話題をさらい、チケットもすでに完売状態だ そうだ。 美和も勿論以前から知っている有名な役者であるが、最近はマヤから聞かされる話しに、彼女の 名はよく登場していた。 マヤとはいくらか年上の彼女は、芸能人としてのキャリアもマヤよりずいぶん格上であるというの に、まるで自分を妹のように可愛がってもらっている、と。 舞台の役の上では互いに対立する間柄なのだが、役を下りればずいぶんとマヤと気が合い、休憩 時間などにもよく一緒に過ごしているのだと言っていた。 「どうぞ…」 美和がお茶を差し出すと、柔らかな微笑と共にありがとう、と言われる。 優しく穏やかな雰囲気。つられてほっとこちらが和んでしまいそうな、不思議なオーラを持った女性 だ。 マヤにもお茶を渡し、しばらく今日の稽古の話しや、硝子の今まで出演した映画の話しなどをした 後、二人のカップが空になりそうになった頃、 「あの、ね、美和さん。また…なんだけど、これからキッチン使ってもいいかなぁ?」 マヤはおずおずと躊躇いがちに、そう美和に問いかけてきた。 どうもここ最近の美和の苦労を思い、さすがのマヤも悪いと思っているらしい。 「え? ですが、雪田さまは…」 戸惑うように言いかけた美和に、マヤはあっさりと言いだす。 「うん、だから硝子さんと一緒に」 「はい?」 そうしてマヤが話し出した事情は、こうだ。 今日の稽古中、休憩の時間に硝子は差し入れだと、マヤや他の共演者達にお菓子を配ったのだそ うだ。 それは薔薇の形をしたクッキー。ほんのりピンクの色をした、とても可愛らしいお菓子で、食べてみ ればさっくりとした食感といい、甘すぎない味といい、非常に美味しく、マヤはどこで買ったのかと硝 子に訪ねた。 すると、なんとこれは硝子の手作りの品だそうで、お菓子作りは彼女の趣味であり、時々時間の合 間をぬって、こんな風によく作るのだと。 マヤの驚きは半端ではなかった。 こんなに美味しくて見た目の綺麗なものが、手作りで出来上がるなんて! そして、いちもにもなく、まるで押し倒さんばかりの勢いで、硝子に頼み倒したのだそうだ。 是非とも自分にお菓子作りを指導してもらえないだろうか、と。 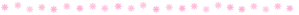 「じゃあマヤさん、はじめましょうか」 「はいっ! よろしくお願いします!!」 マヤは最敬礼のように深々と硝子におじぎをする。 じゃあ…と、マヤはハンドミキサーを手にまず卵の卵白を泡立てようとするが、そこで早々に硝子か らストップがかかる。 「待って!マヤさん。まずは材料を全部準備してからよ」 作業をしながら材料を測ったり、材料を切ったり、そのながら作業というのは料理でよくやる、失敗 の元なのだそうだ。 全ての材料をあらかじめ全部揃えておく、すべてはそれから始めなければならないのだと。 その後も、 「マヤさん、メレンゲはちゃんと泡立ってるかどうか確認するには、ボウルを逆さまにしてみるといい のよ」 「『さっくりとあまり混ぜ過ぎないように』って本に書いてあっても、ある程度は混ぜないとしっかり膨 らまない事があるの」 「本で書いてあるオーブンの温度は、あくまで目安と思った方がいいわ。色々オーブンによって癖が あるから…」 随所に的確なアドバイスを入れつつ、またマヤのドジを見事に起きる前に寸止めしてくれることによ って、これまでとは比べようもない程に、スムーズに作業が進んでいった。 小麦粉の煙幕も無ければ、チョコ礫も飛んでこない。火柱も上がらなければ、もうもうと鍋のこげる 匂いに苦しむことも無い。 美和としては、奇跡を見る思いだった。 そうしてキッチンに香ばしいチョコレートの香りが漂い始めた頃、チン☆という音と共にオーブンを開 いたマヤは、ふんわりと均等に膨らんだスポンジを見て嬌声をあげる。 「うわ〜〜〜、すっごぉい!」 こんなに綺麗に焼きあがったのは初めてで、今までの経緯を思えば、マヤとしても我が目を疑って しまう。 後ろから覗き込んだ美和も、その出来栄えに、思わずあんぐりと口を開けてしまったほどだ。 「ほら、マヤさん。喜んでいる暇は無いわよ。スポンジを冷ましている間に、チョコレートクリームを 作ってしまわなきゃ」 硝子にそう言われ、マヤは喜びで緩んでいた気合を再度入れなおす。 溶かしたチョコレートを合わせた生クリームを泡立て、滑らかなチョコレートクリームを作り上げると、 今度はデコレーションに取り掛かる。 スポンジをハートの形にくり抜き、シロップをはたくと、そこにたっぷりしたチョコレートクリームで丁寧 に飾り付けていく。 ぶきっちょなマヤは、絞り出しの花を何度も何度も失敗したが、硝子は根気よく指導してくれた。 そうして彼女らがキッチンに篭もって実に2時間半が経過した頃、 「で、でぇきたぁぁぁあああ」 マヤの歓喜の雄叫びと、美和と硝子の歓声と拍手が、屋敷に高らかに響き渡った。 その夜、真澄は深夜0時を回る頃、ようやく仕事を終えて帰宅した。 年度末で、いよいよ忙しさも佳境を迎え、このところの彼の帰りは大体この時間ばかりだ。 やれやれ、と真澄がリビングに入れば、そこのソファでクッションに凭れ掛かりながら、すよすよと寝 息を立てるマヤを発見する。 「…またか。まったく、あの子ときたら」 ため息をつきながら、マヤをベッドに運ぶため彼女の体の下に腕をまわせば、直後マヤはうぅん…と 身動ぎし、それまで手に握り締められていた本が、するりと滑り落ちる。 ぱさり、と床に落ちたそれは、今マヤが稽古している舞台の台本だ。 だが、それよりも真澄は意外なものを見つけ、目を奪われる。 台本を握っていたマヤの手。その手が、所々あかぎれ、ひび割れていたのだ。 思わず持ち上げかけていたマヤの体を下ろし、彼女の手を取りよく見てみれば、やはりその手はか なりカサカサと乾燥し荒れており、幾つものあかぎれからはじんわりと血が滲んでいる箇所もある。 確認してみれば、両手共に、だ。 真澄は訝しむように眉根を寄せた。 すると真澄に両手を取られたまま、またしてもマヤは、う〜んと唸り、やがてその瞼がゆっくりと開く と、ぼんやりと寝ぼけた瞳に真澄の姿が映る。 「お目覚めか? 一体何時からこんな所でうたた寝してたんだ」 真澄の声が聞えているのか、しばらくほけっとした表情をしていたマヤだったが、徐々にその目の 焦点が合い、直後はっきりと覚醒した。 「あ…っ、や、やだ! 私ったらまた…っ」 慌てたようにがばっと上半身を起こすマヤに、 「そうだ、『また』やっちゃったんだ。…ったく、俺の帰りを待つな、といつも言ってるだろう。いくら公 演初日までまだ日数があるといっても、風邪でも引いたりしたらどうするんだ! 大体君は…」 くどくどと始まった真澄のお説教を、マヤは焦って止めにかかる。 「ちょ、…ちょっとストップ!真澄さん。あのね、今日は特別なの」 「ん?」 マヤは、待っててねと叫ぶと、隣室から白い箱に淡いサーモンピンクのリボンを結んだ箱を抱えて、 真澄の元へ戻ってきた。 「あのね、真澄さん。これ、すっご〜〜く遅くなっちゃいましたけど、バレンタインのチョコです。今日 まで頑張って、やっとやっと出来たんです! だから、どーしても、今日、真澄さんに直接渡したかっ たの」 いつぞやの様に、はい、と眼前に大きな箱を突きつけられる。 マヤは真澄に身を乗り出すようにして、ほらほらっ、早く開けてみて!と彼を急かす。 「…あ、あぁ」 真澄はその勢いに飲まれるように、少し歪んで結ばれたリボンを解き、その箱を開けた。 すると中からは、ハートの形のチョコレートケーキが現れた。 まわりにはクリームで作った幾つもの花を飾った、まるで売り物のような…とは幾らなんでもいえな いが、それでもちゃんとした、手作りの美味しそうなケーキに見える。 「…すごいな」 マヤの不器用さをよく知る彼として、その思わぬ出来栄えに思わずそんな言葉を漏らす。 真澄の率直な賞賛に、更に勢いを得たマヤは、 「実はね、今日先生に教えてもらったんだ」 「センセイ?」 「うん。硝子さん…あ〜と、今度の舞台の共演者の雪田硝子さんのコトなんだけど。硝子さん、すっ ごくお菓子作りお上手なの。つい強引に教えて下さいっって、お願いしちゃった」 「へぇ、彼女が…」 真澄にしても、雪田硝子という女優はよく知っている。何度かパーティでも顔を合わせた事もある。 「とっても丁寧に教えて下さってね。あ、でも、これちゃんと、最初から最後まで私が作ったんですか らね! 硝子さんも、私が作らないと意味が無いんでしょ…って。味だってね、真澄さん甘いもの苦 手だから、お砂糖控えめにしたんですよ」 意気揚々と嬉しげにこのケーキについて語り出す。さらに箱の中のケーキの花を指さして、 「この花もね、歪んじゃったけど、イチオウ薔薇のつもりなの! えへへ、何回も失敗しちゃったんだ けど、でも…」 嬉々としてしゃべっていたマヤだったが、突然なんの前触れも無く真澄に指差していた手を掴まれ て、言葉が途切れる。 「え? あ、あの…、真澄さん?」 「…もしかして、そのせいでこんなに手を荒らしてしまったのか?」 真澄はマヤの指のアカギレにそっと触れながら、彼女を窺うように覗き込んだ。 瞬間ハッとしたマヤは、慌てて手を引っ込めようとするが、真澄はその手を放そうとしない。 「こんな血が滲むまで手を荒らしたりして… 慣れない事をしたからだろう?」 「あの、…あのねっ、私がいけないの。今日硝子さんにも怒られちゃった…」 そうなのだ。この所妙に手がカサカサとし、やがてアカギレが出来ても、元々自分の事にさほど頓 着しないマヤは、冬だからかなぁとか思いながらハンドクリームを塗る程度でさして手入れもせずに いたのだ。 だが、その手荒れは段々と日を追うごとにひどくなっていった。 何故ならそもそもこの手荒れの原因は、冬の乾燥する時期だから…という理由ではなく、チョコレー トのお菓子を連日作り続けていたから。 それに気付いた硝子に、きつく注意されてしまった。 『マヤさん、あなた女優なんだから、ちゃんと気をつけなきゃダメよ!』と。 もともとチョコレートは油脂の多い食品。 それを洗い流すには、どうしてもお湯と洗剤を多用する事になり、ご多分に漏れずマヤも作っている 間、手にチョコが付くたびに、用具にチョコが飛び散るたびに、お湯と洗剤で洗い流し続けていたの だ。 そうするとこんな風に手が荒れてきてしてしまい、硝子などはチョコレートのお菓子を作る時は、い つも手袋をするようにしているのだそうだ。 マヤの説明を聞きながら、真澄は彼女の中指に出来た深そうな傷を見詰めながら、その端正な顔 を痛そうに歪める。 「俺の、せいだな」 ポツリと呟かれたその言葉に、マヤは大いに慌てた。 「やだっ、だからこれは私が悪いんだって」 「いいや。俺がヘンな事を言い出さなければよかったんだ」 「違うってば!」 ケーキを挟んで、互いに手を握りあったまま、俺が私がと言い出し始める。 幾ばくの間、そんな応酬がなされたのち、そのあまりにも取留めの無い会話がだんだん互いに可 笑しくなってきてしまった。 そして、ふとした瞬間、二人で顔を見合わせてぷっと噴き出し、そろって笑い出した。 笑いが収まって来た所で、マヤはポケットから小さなケースを取り出す。 「これね、硝子さんが手荒れにいいんだって下さったクリームなの。ちゃんと手入れしなさい、って」 マヤはそう言いながら蓋を開けようとするが、その横から真澄の手が伸び、彼女の手からケースを 掠め取る。 そして蓋を開け、クリームをマヤの両手の傷口に痛まないよう、ゆっくりと塗っていく。 「そうだな、君がこんなに頑張って作ってくれたケーキだ。食べさせてもらうよ。ありがとう」 マヤの手にまんべんなく塗り終えると、真澄は優しく微笑みながら珍しく素直な言葉を発した。 「うん。あ、でも無理して全部食べなくてもいいですからね…」 真澄の言葉に、マヤは少しテレを混じらせながら、それでも嬉しそうに顔をほころばせた。 「食べるさ。『ぜんぶ』」 そう言ったと思ったら、真澄は膝の上に置いていたケーキをマヤに持たせ、え?という顔をしている 彼女を、あっというまにひょいと両手に抱き上げる。 「うわわわ、落ちる」 「ほらほら、ちゃんと落さないように持っててくれよ。俺のなんだから」 「ちょっと、何なんですか。イキナリ」 「ん?何って、決まってるだろう。『ぜんぶ』美味しく食べようかと思って」 「え?」 きょとんと首を傾げるマヤだったが、そのまま真澄がスタスタと寝室に向かうのに気付き、ぼっと一 気に頬を染める。 「食べて欲しいのは、ケーキのほうだよぉ…」 腕の中で小さく呟かれた言葉に、 「先に食べたい」 耳元で囁かれる、ケーキよりも、もっともっと甘いヒトコト。 2月14日から実に3週間が経過した頃、こんな風にしてやっとマヤのバレンタインは終了したのだっ た。 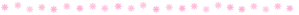 ようやくマヤのキッチン戦争が終結し、美和はこれでようやく落ち着いた…と胸をなでおろしつつ、 頼むからしばらくはこのまま平穏な日々が続いてくれ!、と祈るような気持ちでダイエットに励んで いた。 真澄もやはり年度末で毎日忙しい日々であったが、お目当てであったマヤからの手作りが貰えた 事で、ほくほくと幸せ気分であったのだろう。 珍しくこの夫婦の口げんかもなりを潜め、速水家は一時的に穏やかな空気が漂っていた。 だがしかし、その平和も長くは続かなかった。 それは、マヤのチョコレートケーキが無事完成した、ちょうど1週間後の事。 屋敷にまたしてもマヤの大声が突き抜ける。 「しんっじらんないっっっ!!」 お茶を手に、扉をノックしようとしていた美和は、マヤのその声に、ぴたりと手を止めた。 「なによっ、真澄さんなんか、きれいさっぱり忘れてたくせに!!!」 部屋の中からは、再度マヤの叫び声が漏れてくる。 「勝手にしろっ!」 真澄の怒りの混じった様な一声に被さるように、 「ふんっ、だ。勝手にしますよ〜〜〜だ! これはね、皆さんがお返しだってわざわざ私にくださった んですからね。全部きっちり私が食べるし、頂いたものは大事にするもん!!」 そんな声と共に、扉のノブが動き、中からマヤが飛び出してきた。 マヤの両手には大きな紙袋が4つ。 その中には、色とりどりの包装紙に包まれた大小さまざまな箱やら袋がぎっしりと詰め込まれてい た。 今日の日付は、3月14日。 世の男性が、バレンタインデーでのお返しをするべき義務を負うホワイトデーなる日。 1ヶ月前山のように配ったマヤからのチョコレートに、倍返しとばかりに山と返ってきた彼女宛の贈り 物。 美和の姿を認めると、マヤは憤慨しながら、 「聞いてよ、美和さん! 真澄さんったら、ひっどい事言うのよ。折角今日こんなに沢山頂いたもの を、そんなもん捨てろ、だって!!!!」 ……あいたたたた。 「真澄さんなんか、今日ホワイトデーって事も、ぜぇんっぜん覚えてなかったくせにっ!」 見れば扉が開いたまま、部屋の中では聞えているだろうマヤの叫びを、あえて知らん顔をしながら そっぽを向いている男がいる。 「私が、あんなにあんなに頑張ってケーキつくったのに、真澄さんが欲しいって言うから作ったのに、 一生懸命バレンタインしたのにぃぃ」 興奮しているマヤは、美和に口を挟ませる隙も与えてはくれない。 というより、美和に言いながらも、本当は背後の真澄に対して聞えるように言っているのに違いない のだ。 そうして、とどめの一発。 「お返しも忘れて、その上そんな事言うなんて……もう、もう、真澄さんなんか、大っっキライッ!!」 合掌…──── 叫んだ直後、がさがさ紙袋をかさばせながら自室へと駆け上がるマヤと、苦虫を噛み潰したように リビングでひとり佇む真澄の双方を眺めやりながら、美和は体中から吐き出すように、深々と、脱力 のため息をついた。 <Fin> |
   |